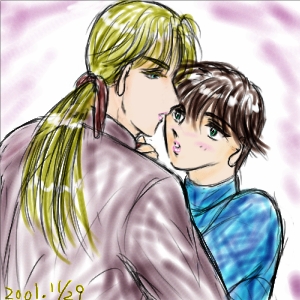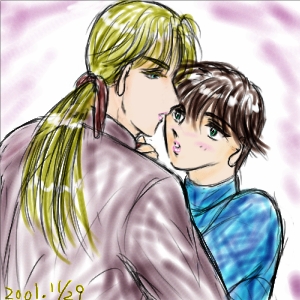
|
メディオンにとって、シンビオスは『魅惑』の塊だった。 ちょっとした表情や動作や声など、他の誰かが同じようにしても何も感じないのに、これがシンビオスだとメディオンの胸は騒ぐのだ。 殊に周りに誰もいないときには、シンビオスの前ではメディオンの理性などあってなきがごとし、という感じだ。 もう既にお互いの気持ちを確認済みの二人だが、実はいまだにキスさえも済ましていなかった。何故かといえば、メディオンがさり気ない口説き文句を台詞の中に交ぜてみても、シンビオスはまったく反応しないからだ。とんでもなく鈍いのか、またはメディオンに何も感じていないのだろうか。もし前者なら、もっと直截的な行動を示す、という対策がある。しかし、後者ならメディオンにはどう仕様もない。 そこで、メディオンは確かめてみることにした。シンビオスの目をじっと見つめて、彼の手に自分の手を重ねる。 シンビオスは大きな目をくりくりさせてメディオンを見つめ返すと、 「メディオン王子、なんですか?」 とにっこり微笑みかけてきた。まるで邪気のない笑顔だ。 これは効いた。メディオンは真っ赤になって手を引っ込めた。 「い、いや、なんでもないんだ」 「……………?」 シンビオスはちょっと小首を傾げた。不思議そうに目を瞬かせている。その風情がまた可愛らしくて、メディオンはいたたまれなくなった。このままでは、シンビオスを無理矢理どうこうしてしまいそうだ。彼の心も体も傷つけるようなことはしたくない。 「…あー、そういえば、ちょっとキャンベルに用事があったんだ。シンビオス、待っていてくれるかい?」 曖昧に言って、立ち上がる。 「はい。----すぐに戻ってきてくださいね」 メディオンの心を知らぬげに、シンビオスは明るく答えた。メディオンは少し引きつった笑みを返して、自分の部屋を出た。 キャンベルを見つける前に、メディオンはジュリアンに会った。彼も経験豊富だから、何かいいアドヴァイスがもらえるかもしれない。メディオンは早速彼を人気のない所まで連れていった。 メディオンの話に、ジュリアンは大笑いした。予想はしていたものの、面白くはない。メディオンは顔を顰めて、 「私にとっては笑い事じゃないんだが」 「----ああ、そうだろうよ。でも、可笑しいよな」 ジュリアンの笑いは止まらない。メディオンは溜息を一つついて、忍耐強く待つことにした。 やがて、ジュリアンは疲れたらしく笑うのを止めた。 「----しかし、あんたも案外奥手だな。有無を言わさずに押し倒しちまえばいいのに」 大きく息を吐きながら言う。露骨な表現に、メディオンは眉を寄せた。 「君じゃあるまいし、無理矢理なんて性に合わないんだ」 「そんなこと言ってたら、一生このまま清い関係で終わるぜ?」 ジュリアンは揶揄するような口調で、 「シンビオスって、そういうことに異様に鈍感だろ。----つうか、自分がそういう対象として見られてる、なんて考えもしねえんじゃねえか?」 「それは確かに…」 メディオンは心の底から頷いた。だからこそ、メディオンがモーションをかけたにも関わらず、さっきみたいな無邪気な反応を返すのだろう。 「ちゃんと解らせてやれよ。あんたがシンビオスに対してどういうことをしたいのか、さ。怖がるかもしれねえが、そんなのは最初だけだ」 ジュリアンはにやりと笑った。 「あんただって、このまんまじゃ堪んねえだろ」 「そりゃあね」 メディオンは短く答えた。確かに、シンビオスが無意識のうちにする『誘惑』に対して、いくら人より辛抱強いメディオンといえども、そろそろ限界に近い。 「ま、せいぜい頑張れよ」 言葉と共に、ジュリアンはメディオンの背中を押した。メディオンは礼を言って、シンビオスの待つ部屋に戻った。 ----とはいうものの。 部屋に入って、シンビオスの可愛い笑顔に迎えられると、メディオンはどうにも緊張してしまう。ぎこちない足取りで、席に戻ろうとしたが。 シンビオスが椅子から立ち上がった。そのままメディオンの方に歩いてくる。メディオンは立ち止まって、心持ち身を引いてしまった。 「シ、シンビオス----」 シンビオスはメディオンの襟元に手を伸ばして、 「リボンタイがほどけてます。----動かないでくださいね」 「あ、ああ…」 メディオンの声も体も、銅像のように強張っていた。シンビオスの柔らかい髪が頬をくすぐる。指先が首筋に触れる。ちょっと腕を伸ばせば、シンビオスの体はやすやすとメディオンの腕の中にくるみ込まれるだろう。メディオンの心臓は早鐘のように激しく鼓動していた。何度も腕を上下させる。まだためらいが残っていて、思いきった行動に出られない。 「----はい、終わりましたよ」 シンビオスが顔を上げて、メディオンに微笑みかける。それがとうとう、メディオンの理性を砕いた。 メディオンはシンビオスを引き寄せた。腕の中にきつく抱き締める。 「…あ…」 シンビオスはメディオンの胸に両手を預けるような体勢で、身を縮めている。やっと、我が身に起こった事態を呑み込んだのだろう。みるみる顔が紅くなっていく。メディオン同様、鼓動も速まっているのが感じられる。 メディオンはシンビオスの顔を仰向かせた。彼の潤んだ緑色の瞳の中に、自分の姿が見える。 「あ、あの…、王子----」 「…目を閉じて」 メディオンは顔を寄せ、シンビオスの少し開いた唇に深く口付けた。 「----ん…っ」 シンビオスが小さく声を漏らす。メディオンの腕の中で震えていた体が、その力を抜いていく。今や、メディオンに全身を預けるようにもたれ掛かってくる。 「----シンビオス…」 メディオンは、紅く染まったシンビオスの耳に囁いた。 「後でまた、タイを結び直してくれるかい?」 「あ…。は、はい…」 シンビオスは恥ずかしそうに頷いた。 |